■トップに戻る
■本編トップへ
■フォントサイズの変更:
- 30・思い出
- 31・兄弟
- 32・悩み事
- 33・悪魔の匣の中
- 34・罪と罰 上
- 35・錬金術士と時の巫女
- 36・罪と罰 下
- 37・静かなる戦い
- 38・その心は猫をも殺す
- 39・彼らの話
- 40・宣戦布告
- 41・最初で最後の円舞曲
- 42・翻る反旗
- 43・熱
- 44・青と赤
- 45・ゆらぎ
- 46・姉妹と回想
- 47・夜曲
- 48・鬨の声
- 49・答え合わせ
- 50・必ずあなたを
- 51・花と花守
- 52・銀色の記憶
- 53・使命より何より 上
- 54・使命より何より 下
- 55・ミクス
- 56・紅い目の男
- 57・アリア・レコード
45話「ゆらぎ」
本部で慌ただしくしていたサクヤの元に、暗黒地帯の調査をしていた部下からの電報が届いた。通信機があるのになぜ電報なのかと思うかもしれないが、訳あって通信機が使えないのである。
しかし問題はその内容にあった。
サクヤは震える手を握り締めると、とある男に会いに行った。
◆◇◆◇◆
暗い悲しみの深海。あの時触れた冷たさが今になって刺さる。
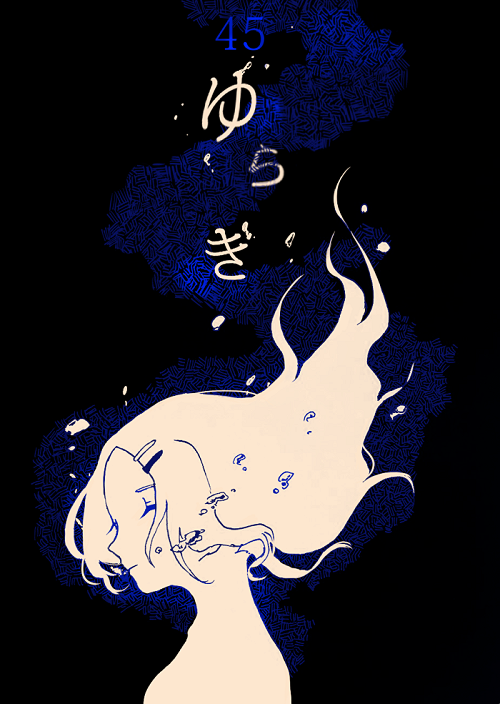
【スヴェーア レディの研究室】
目が覚めた時、そこはソファーの上だった。クッションが黒い滲みを作り、己の頬は濡れている。どうやら泣いていたようだった。
部屋の隅の一角、キッチンでレディはお湯を沸かしていた。
「珈琲は飲めるかい?ああそれとも水がいいかい?」
くつくつとヤカンが音を立てる。水を汲んだレディがコップを持って来るのを、アルモニカはゆらりと見上げる。
「あなたは分かっていたの?」
「ああ」
「ならどうしてこんなこと!」
荒ぶる声、踊る水滴、けれどレディは涼しい顔で言ってのける。
「もしワタシが冷徹で頭脳明晰だったら、知ってすぐ彼を殺していたよ」
「……!」
アルモニカはへなへなと座り込んだ。
レディはすっかり中身が半分になってしまった水の入ったコップをテーブルに置いて、「珈琲を淹れてくるね」とキッチンへ消えた。
夢に似ていたけれど、違う。目覚めて時間が経っても薄れることはなく、はっきり思い出せる。
赤い電球が照らす薄暗い研究室、白衣を着た黒髪のやつれた男が何かを渡していたこと。また別の日、それを受け取っていた白いスーツの男が崖で誰かと話していた。そして手の中の物を胸に叩き付けて冷たい夜の海に突き落としたこと。悪魔達が探し求める人間を滅ぼす花というのは海に落ちた彼のことで、それが、よく知っている人物だということ。
胸が張り裂けそうだった。自分が死ねば世界が救われる?一体どんな気持ちなのだろう。寧ろそれなら良かったのではないか。しかし実際はどうだ?自分のせいで世界が滅ぶなんて、多くに死を望まれるなんて。なんて深い絶望なんだろう。いつから知っていたんだろうか。知っていながら、正気を保ち、いや、平常を装っていた気持ちを考えると、苦しくて堪らない。知らなかった、何も言ってくれなかった。だけどそんなこと言えるはずがない。誰も悪くなんかないのに。それなのに、心の中で責めた。謝りたい。頭がぐるぐるしそうだ。
珈琲を淹れてきたレディは、その一つをアルモニカに手渡して隣に座った。
おとなしくソファーに珈琲を啜っていたアルモニカだったがやがてぽつりと零す。
「苦い」
「苦味の強い豆が好きでね」
コップを膝に置いて、レディは語り始める。
「さっき知っていたなんて言ったけどね、本当ではないんだ。全て把握していたわけではない。……びっくりしたよ。悪魔達の言動から推測して花というものが存在することは分かっていて、それをずっと調べてはいたんだけどね。それが誰なのか、いや何なのかさえ分からなかったんだ。そしたら事実はこうだった。同じ組織内にいたなんてね。まさに灯台下暗しってやつだね」
彼女はアルモニカに向き直った。青い瞳が怪しく光る。
「君はどう思う?人類を救う為、君は彼を殺すことができるかい?いや逆だ、彼がいなければこのような危機にはなり得なかったんだけども」
レディの言葉の棘など、アルモニカには届いていなかった。
記憶の中の彼は泣いていた。真っ白な世界で、泣きながらも晴れやかな表情だった。そして、表情も分からず、会話さえできなかったあの夜が蘇る。どうして黙って行ってしまうのか、理解ができなくて追いかけられなかったが、もう迷わない。立ち止まらない。彼女は、青い瞳を真っ直ぐ射抜く。
「このままだと人間は、死ぬんでしょう?でも、遅かれ早かれ人間は死ぬ。その時間がはっきりしただけよ。救うほどこの世界は立派?人間は立派?救う道を選んだとて、こんなにどうしようもなく腐りきった世界で私達は幸せになれるの?」
「言うね。まるで世界に自分しかいないみたいな発言だ」
「それまでの時間、ほんの少しでいい。話がしたい。その時が来るまで」
アルモニカは目を伏せた。
「君は傲慢だ。何もかも思い通りに行く筈がない。その言動をワタシが許す筈もない。けれど気に入ったよ。良いだろう、少し待ってあげる」
そう言い彼女は立ち上がった。そして振り返ると目を細めた。
「……だけど悲観する必要は無いよ。何も彼を殺さないと世界を救えないと言ってない、その方法がまだ分からないだけで。彼は諦めずに探しているよ。助かる方法を」
「ある……の?」
「きっとね。彼にも言っておいたよ。君は彼を追いかけるのがいいと思う」
向こうも動いてるしどこにいるかは明確に分からないんだけど、と彼女は肩をすくめる。
それから彼女は側に置いてあった鞄を掴み上げ棚に向かうと、鞄に幾つか瓶を詰め始めた。その様子を見ていると、ふと手を止めた。
「ああ、花守がいたらねえ」
「花守?」
聞き覚えのある単語だった。
「うん。花の種と同時期に造られた存在。花守は花を守らなければいけないから、位置が分かるんだ。だから花守に聞けばいいんだ」
「それが、いない?」
「うん。――花の種は人間に宿さないと効果が出ないことが分かっていたから人に宿されたけど、花守は悪魔なんだ。花の種の所在を掴み手元に置いておく為、花守は悪魔がやるのが良いだろうってそうなったんだろうね。でもワタシのリサーチによると、花守がうまく適合せずに、その悪魔は死んでしまったらしい」
「……」
「まあそんなに悲観することはない。花を探すのも花守を探すのも手間は一緒さ。大体どの辺に向かったかは教えてあげるから行っておいで。ワタシは本部に行ってくるよ」
レディは鞄を背負い、共に地下室から出る。
方位磁石を取り出したレディは、方向を確認すると、パチンと閉じて、アルモニカに溌剌とした笑顔を向ける。
「じゃあね!ワタシは君の鞄をフィルグラードまで届けて来るよ。君はあっち!少し下れば道に出るから迷わないだろう」
南の方を指差す。駅のあるアレクセイエスクだ。足を踏み出しかけて、彼女は付け足した。
「そうそう!君の母親の過去を移した瓶があったんだけど、うっかり花の種に渡してしまったよ」
突然の母の話題に、思わずビクリとした。
「どうして……?」
「期待?報酬?かな!君が追いつけば過去を知ることができるんだから。まあ、そんなことしなくても君は追いかけたのかもしれないけど」
「それって、私に追いかけさせようとしたってことですか」
「さあね」
ピエロは眉を上げて肩をすくめた。
「走る時は竜胆を使いなね。分かっていると思うけどあれは特に速いから。『孤独な貴方』の元へ、真っ先に駆けつけて共に戦う為に」
ヒュールの雅京は最速の武器。速度にステータスを重く振ったせいか、故に火力は物足りず繰り出す攻撃は決め手に欠ける。けれどそれは、一人で戦う為のものではなく、誰かを支えるためのものだった。
◆◇◆◇◆
【ヴァルニア 本部】
「暗黒地帯が拡大を見せているのは、この装置が原因かと思うのです」
レイの帰還直後に行われた武器使い達の会議で、彼らは彼女の持ち帰った物体を、ある者は興味深そうに、あるものは訝しげに眺めた。
テーブルに置かれたのは、三十センチ程の銀の筒。レイの手によって既に破壊されている。
「暗黒地帯で見つけたのです。これを移動させると、暗黒地帯が移動しているようなのです。持ち帰るのに破壊したのですが、その前は青い光を放っていたのです」
本部の危機に駆けつけた、南部エクソシスト隊の隊長ジェイルは、ほう、と腕を組んだ。
「高度な技術によって作られてるって訳だそれは。無機物、そして物理的に破壊できた所から推測するに、悪魔とか武器絡みでも無さそうだな」
レイは頷き、「更に、」とその筒を重そうにひっくり返した。土が僅かに付いたままの底に刻まれた記号に、彼らは見覚えがあった。
「つまりこれは暗黒地帯を発生させる装置、そして、ここに刻まれた刻印は、研究社ピコ製であることを示すもの。暗黒地帯を発生させていたのは、ピコです」
サクヤは、その言葉に動揺した。ざわつく中、咳払いをして手を挙げた狐面の男はグレイヤー。
「……私が考える一つの可能性について語ってもよろしいですか?」
苦い顔をしたままのジェイルが、どうぞと促した。
「研究社ピコは私達には理解のできない程の技術力を持っています。いや、独占しています。
教団が世界的に力を持つことができているのは、純粋な武力、大義名分の他に、技術力を持っていることにあります。それはピコの後ろ盾があるからこそ成り立っていたことでした。ピコの提供する技術以外からは、それらしき発明は生まれていません。大方、彼らは技術者を何らかの形で発見し回収しているのでしょう。
周囲に邪魔されず研究をする、技術力の独占の為、世界の技術発展を妨げる……。その為に必要だったのが暗黒地帯。あれのおかげで私達は、物流も情報の行き来も少ないですから。あれが無ければ都市と村の格差もここまで酷くはならなかったでしょうし、いずれ起こる戦争と共に技術も発展したでしょうね」
「……話が大きすぎて俄に信じ難いが……。では、暗黒地帯が拡大しているというのは、彼らが我々一般人の交流を更に制限しに来たということか?」
「もしくは、俺らが本部に集まるのを遅らせる、みたいにな。黒の瓶の製造は本部でしかやってねえし。その製造ラインも止まっちまったし」
腕を頭の後ろで組んだジェイルがそう言った。
「何故そんなことを?」
「何故でしょうね」
しらを切る狐。サクヤはいたたまれず席を立つ。
その様子を気にしつつも、レイはグレイヤーに質問を投げかける。
「ガーディの後ろ盾という可能性はないのですか」
「ガーディは教会側の組織。ピコはメルデヴィナ教団に技術、資金援助という形でエクソシストに武力を行使させる。その実悪魔を野放しにしている。この目的は、エクソシストが悪魔を討伐しているというパフォーマンスをさせるためだと考えられます。ここから得られるのは、悪魔と人間の戦うだけの世界。その裏で何が起こっているのか、人々は知る由もなく、悪魔に怯え教団を盲信するのです」
「……それは憶測なのですか」
「憶測です」
「ま、要するに、裏でやってることの邪魔をされたくないから、その為だけに俺らは利用され続けてきたってことだ。人間だけじゃなく、もちろん悪魔にされた奴らもな」
「……もう一度言いますが、ガーディは教会側の組織で裏にピコが付いています。悪魔とエクソシストが闘うというパフォーマンスをガーディによって終わらせ、その次の世界を作ろうとしているということです。そして、その舞台の上で踊らされているだけの私達。逃げることもできなければ、この先進んで台本があるのかさえ分からない。けれど進むしかないのですよ」
口をまっすぐ結んでグレイヤーの話を聞いていたレイは、暫しの沈黙の後口を開く。
「あんまりなのです。あなたは、ボク達にこのことを伝えるべきでなかった」
「憶測です。それに、あなたは何となく気付いていたのではないですか?この装置を見つけた時から」
「……まるでこの世界の神様があの組織みたいなのです」
「その神様がこちらに直接手を下そうとしているのですよ。その手、掴んで引きずり下ろしてやれるんですよ」
ジェイルが茶化す。
「おー怖。流石血の武器の使い手は違いますわ」
「ジェイル、」
「……そうですね」
俯いたまま部屋を出ていってしまったレイの背を見ていたジェイル。扉の閉まる音。
「お前さあ、これで良かったの?士気を下げちまうなんてらしくない」
「ええ。彼女ならきっと大丈夫ですよ」
「想定内って訳か……。サクヤ・ロヴェルソンも?」
「彼女は……少し話す必要がありそうですね」
「はあー大変そうだなあ」
「あなたもやるんですよ!」
「えー?俺は戦場でしか役に立たねえ脳筋だし」
「そんな訳!無いでしょう!本当はとても器用なくせに!早く一般隊の説得に行ってください!」
「えっそれもまだだったのかよ……」
「んん……レイクレビンという男が出ている間にやる必要があったのですよ」
「なるほどね……」
一方部屋を出ていたサクヤは、数時間前のことを思い出していた。
その男のことは知っていた。カナソーニャ・ロヴァイ研究所跡地で出会ったのが初めてかと思っていたが、実はそうではなかったらしい。
本社はテトロライアの西の隣国ルティア公国にあった。中世の街並みを色濃く残すテトロライアと違い、僅かながら時が進んだ印象を受ける。テトロライアが鎖国よろしく国境に塀を築いているせいで東の人間は気付きにくいのだが、大陸の西方世界は、大部分の東と一部の西で随分と毛色が違う。それを如実に表しているのがピコという存在だった。
会社に赴き名前を出すとすぐに本人に通された。案内されたのは、嫌になるほど綺麗で日光のよく入るテラスだった。幅の広い椅子に優雅に座った社長……シリスが脚を組む。
「うーんどうやらうちの機械が暴走しているんだね。迷惑かけて大変申し訳ない」
「迷惑?……いつまでしらを切るつもりだ」
「へえ?変な事言うね。でもね、知ったこっちゃないね!君らは君らでやることがあるかもしれないけど、僕らは僕らでやることがあるからね!第一教団組織内の仲間割れなんて、援助してる僕らの知る所ではないんだけど?」
眉を顰めたサクヤは迫る。
「預かり知らぬと?あなた方がこう仕向けたのに?」
身を乗り出したサクヤを、口元は笑ったままギロりと睨む。
「それは憶測では?」
「……そうだ」
大きく息を吐いて、シリスは椅子にもたれかかった。
「失礼な人!じゃあもし君の思う通りだったとするよ。で、そのガーディとやらが僕らの組織だったとするよ。……なら勝てるとでも思っているのかな、我々のガーディに」
「もちろん勝ってやる」
「ふふ、やってご覧よ」
ピリピリとした空気の中、パッとシリスは両手を上げて溜息をつく。
「嘘嘘。今のは例え話でしょ。――そもそも君ってさ、その場合どうするの?君はうち出身だよね?仲間と戦うことにならない?」
サクヤは首を振る。
「ここに仲間は、もういない」
「へえ……」
細い目を更に細めてシリスは首をかしげた。
「でもいいの?もし今から君らが戦う相手が僕らだとしてさ、それを吹聴するのはまあ一万歩譲って構わないよ。でもそれって君にとって損じゃない?うち出身だと周知されてる君が信用される訳なくない?スパイだとかさ」
「……」
実は既にそんな話はあった。悪だと仕立て上げられたピコから来た人間だと、文官や一般隊を交えた会議中に、的にされたことが。
シリスは怪しく微笑む。
「なんてね。すごく不毛だし有り得ない話はやめようよ。でも、まあ、その表情から察するに……彼らが嫌になったら帰っておいでよ。受け入れ先は用意しておいてあげるからさ。いつでもおかえりと言ってあげる」
「……そんなの、いらない」
聖母のような微笑みに、ふいと顔を背けて立ち去った。
◆◇◆◇◆
【赤い部屋】
部屋の一角にある姿見。その前でふと立ち止まった十代後半ほどの少女は、じっとその姿を見つめる。
鏡の向こうの金髪の少女は、ふわふわとしたロングの髪の毛先を弄りながら喋る。
「髪の長い方が可愛い?本当?でも、いつも邪魔だよ?闘うのに長い髪の毛なんてさ。邪魔にしかならない」
手袋を嵌めながらその後ろ姿を見ていた黒髪の女性……ミカミは、さして気に留めていなかった。しかし少女の傍にハサミがあるのがいけなかった。
「やっぱり髪の毛邪魔だなあ。切っちゃおうかな。えい!」
右手のハサミが閉じると同時に、彼女の左手で掴んだ髪の房が随分と短くなった。
「こらなにやってんのよ!」
「え?」
血相を変えて飛んできたミカミに右手を取り押さえられる。しかし振り向いた少女……ミクスは、とても不思議そうな顔をしてミカミを見つめる。
「どうしたのミカミ」
「何で、こんなことしてしまうのよ」
「邪魔だし」
「……はあ。もっと何かあるでしょ。こっち来なさい」
溜息をついたミカミは、彼女をドレッサーの前に座らせて、その後ろ髪を結い始めた。
「そういう時は結えばいいのよ」
「えー?」
「動くんじゃないわよ」
手際のいいミカミによって、彼女はポニーテールになった。
「わあー。邪魔じゃないね!」
手を離されて、ぱっと鏡に近付いたミクスは、頭を左右に動かし、揺れるポニーテールを観察して楽しそうであった。
「で、さっきの会話の続きだけど、あんたのやりたいことって何なの」
振り返りきょとんとしたミクス。
「そんな話してた?」
「してたわよ!あんたが急に鏡の方行っちゃうからちょっとびっくりしたわよ」
えへ、ごめんね?とミクスは笑う。
「うーん。あ、そうそう。ミクスが、一番大切に思ってた存在を殺すこと。ついでに褒めてもらうこと、かな」
「?あんたはミクスじゃない」
「えへ、そうだね」
少し妙なことを言ったが、彼女はいつもと変わらなかった。ミカミは首を傾げて「変な子」としか言えなかった。
「そろそろ行くわよミクスちゃん。きっとみんなを待たせているわ。準備はばっちり?」
「勿論!あ、待って」
「?」
ミクスは窓から下を覗くと、方向を変えいそいそと部屋を出ようとする。
「ちょっとその前に、妹にちょっかいを出してくる!」
「はあ?」
「うふふ」
振り返った彼女は悪い顔。ミカミは気になり窓から下を覗くと、中庭に、たまに見る金髪の子供が佇んでいた。
「塔の目の友達ね。そろそろ王子様が帰ってくる頃かしら。まあ……兄弟姉妹の問題には首を突っ込まないで置きましょう。放置するのが無難だわ」
そうして窓から視線を部屋の奥に向ける。
そこには年端もいかない女の子が椅子に座っていた。赤い制服の上から赤いケープを身にまとい、その目はじっとミカミを見つめている。
「でもあなたは不服そうね。塔の目ちゃん」
◆◇◆◇◆
閑話「レディと一番隊」
「たーだいまー!」
騒がしかった会議室は静まり返り、扉を開け放ったレディに複数の視線が突き刺さる。それは冷たいものではなく驚きに満ちたもので、特に会話の中心にいた禿げかかった頭の男は、信じられないといったような表情でゆっくり歩み寄る。
「レディ……隊長?」
「うん」
「帰って、」
「ああ。苦労をかけたようだねリダちゃん」
「ああ……」
ずっと張っていたのであろう気が緩んだ男……リザヴェーダはその場で卒倒する。
「リダちゃん!しっかり!」
近くにいたピンク髪ショートの小柄な少女が彼に駆け寄り抱き上げると、久々のご帰還を果たしたレディを見上げる。
「おかえり隊長!もう、急に帰ってきて驚かせないでよね!リダちゃんびっくりしちゃう」
「はは、ごめんね」
「さっき悪魔が出たって聞いて、イズミに行ってもらったんだけど誰も見つけられなくて……そのこともあってリダちゃんちょっと今ナーバスなの」
「その問題は大丈夫だよ。解決してきたから」
「さすが隊長!」
その時、はっと声がして、ピンク髪娘チュコの腕の中のリザヴェーダが覚醒する。
「寝ている場合ではありませんでした。隊長、本部が」
「ああうん、ご存知よ」
そう右手を軽く挙げた時、ふと自分の持ち物を思い出す。
「そう言えばリダちゃん。こっちに落し物?取りに来た人いないかい?黒い鞄なんだけど」
そう言い鞄を取り出す。
「ああ。そう言えば先ほどリルベルナ氏という方がいらっしゃいましたよ。待合室にいるので呼んできますね」
そう言い退出したリザヴェーダの背を見送り、チュコは鞄に手を伸ばす。
「おや?手癖の悪い子だ」
「いいじゃない。ちょっと気になることがあっただけ!――あのおじさんね、まだ戻って来てないから、届いたら送りますから一旦帰ったらって言ったのに待ってるって言ってたんだ。待合室で暫く話し相手になってたんだけど、あの人は離婚して独り身な上、子供を事故で亡くしてるんだって。すごい幸薄い人……。演劇は喜劇より悲劇の方が好きなんだ。でも本当はメロドラマ。とってもそんな予感がしない?」
「しない」
「で、その鞄には大事な娘ちゃんの写真が入ってるんだって。さてどんな美人さんなのかしら。女の子は三歳の時可愛ければずっと可愛いんだよ」
レディは溜息をつく。
「よく分からないけど、リダちゃんにバレないようにした方がいいね」
「勿論!勝手に中身を漁ったなんて知れたら怒られちゃう!果てには倒れちゃうかも……」
そう言いつつ取り出したのは一枚の写真。古ぼけたそれに写っていたのは、抱きかかえられた赤ん坊。
「なんだ……これじゃ分かんないよ……」
「分かるよ。今と変わらず美人じゃないか」
「?」
「あー!」
扉を開けたリザヴェーダが叫び、慌ててチュコは諸々を乱雑に鞄に入れて差し出した。
「ごめんなさいおじさん!」
「プライバシーとは……私が、すぐにあやまる……うっ胃が痛い……」
急激なストレスを感じたリザヴェーダは混乱し突然胃薬を飲み始める。恰幅のいい紳士は、「構わないよ」と笑いながらそれを受け取った。
謝辞を述べた紳士が立ち去りリザヴェーダの胃痛も治まった頃、チュコがねえねえ、とレディの袖を引っ張った。
「さっきのどういう意味なの?」
「大した意味ではないよ」
レディは微笑んだ。
「それより君たちこの組織のことをもっと心配した方がいいんじゃないのかい?ワタシはもっと慌てていたと思ったよ」
「隊長が帰ってきたんだもん!もう安心!ね、リダちゃん!」
チュコはバンと背を叩く。濁った瞳のリザヴェーダ。
「ええ……もうしばらくは胃薬を買わなくて良さそうですし、私が戦いに参加しなくても良さそうです……」
「リダちゃんは武器使いなのに本当に武器使うのが嫌いなんだから」
「エクソシストなんか知らない。一生事務作業をしていたい」
「うん?あなたもワタシと来るんだよ?」
「は?」
間抜けな声を出したリザヴェーダに、レディはもっとゆっくりと言う。
「イワノフ・セルゲーニヴィチ・リザヴェーダ、あなたもワタシと本部に行くよ」
「何故言い直したんです?!」
「大事なことなので二回言いました」
「ここテストに出るよ!」
「出ませんよ!テストにもここからも!」
「馬鹿を言っていないで行くんだよ」
「やだ!やーだー!」
珍しく駄々をこねる中年男性を連行していくレディ。そして彼らに手を振るチュコ。
「あたしはみんなとここを守るね!頑張ってきて隊長!絶対信じてるから!……あっリダちゃんも!」
「おまけ……」
「リダちゃーん!胃薬はきっと向こうでも買えるよー」
これから向かうのは戦場だと言うのに、彼らは非常に賑やかだった。それは己の隊長にかける絶大な信頼があるからだろう。
「でも、世界が今のままでなくなるかもしれないなんてね、知らなくていいだろう」
「レディ隊長?何か言いましたか」
「いいや。何も」
(閑話:終)
46話へ









