■トップに戻る
■本編トップへ
■フォントサイズの変更:
- 30・思い出
- 31・兄弟
- 32・悩み事
- 33・悪魔の匣の中
- 34・罪と罰 上
- 35・錬金術士と時の巫女
- 36・罪と罰 下
- 37・静かなる戦い
- 38・その心は猫をも殺す
- 39・彼らの話
- 40・宣戦布告
- 41・最初で最後の円舞曲
- 42・翻る反旗
- 43・熱
- 44・青と赤
- 45・ゆらぎ
- 46・姉妹と回想
- 47・夜曲
- 48・鬨の声
- 49・答え合わせ
32話「悩み事」
「さあルクス。行くわよ」
「いやだ!そっちはいや……!」
「どうか困らせないで」
「いきたくない、おねがい」
ぐずる子供を目の前にして女は、悲しい顔をして膝を折ると、その子供の顔を見つめた。
「……ごめんね、何もできなくて」
そう言い白衣の女は子供を抱きしめた。
◆◇◆◇◆
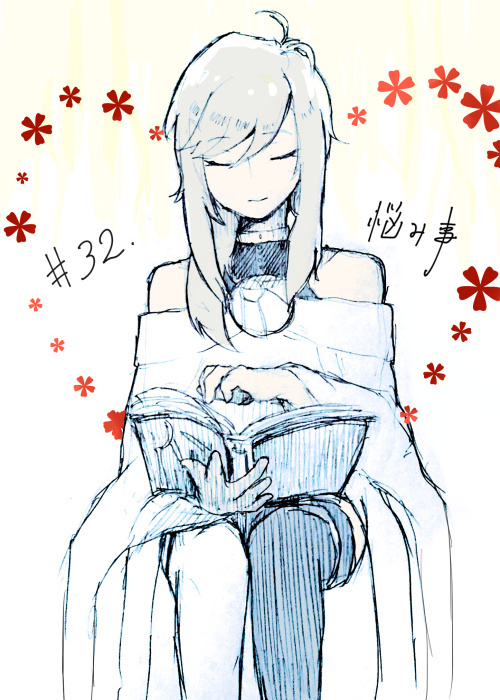
目を開くと、薄い青の世界が広がっていた。
ここはアリア・レコード。アンリの夢の世界。目の前にはいつものように、エメラリーンが椅子に座っていた。目を伏し本の頁を捲っている。
部屋の景色は時に変わる。そしてエメラリーンさえも。確かに、彼女の椅子はただの木の椅子であったり、石の玉座であったり様々だったが、今日はまた随分と簡素な椅子だった。
ふと、彼女は顔を上げた。
「ようこそいらっしゃい。私の愛するアリア・レコードへ」
「久しぶりだねエメラリーン」
「そうでしょうか」
エメラリーンは白い瞳を細めた。
ふと部屋に注目すれば、部屋の青はいつもより淡い。代わりに、と言うのだろうか。部屋には植物の根のようなものが張っていた。天まで届くような本棚にまで。その根は本と本の隙間、その表面を這っている。
「お気付きでしょうか。競合しているのです。ここもこんなに根が張ってしまって」
「つまり……ここは、単なる夢じゃない……?」
「さあ」
エメラリーンは膝の上の本を閉じ、足元に置く。そしてアンリを見据えた。
「もう、あなたとは会えなくなります。ここでは、ですが」
突然に別れを告げられ、驚いたアンリは立ち上がった。
「どういうこと……?この部屋が無くなるの?もうこの夢を、見なくなるの?」
「私はあなた。あなたは私。この部屋もまたあなた自身なのです。私はいつでもあなたの側におります。ただこのように、あなたと対話することが無くなるだけ」
「そんな……」
別れはいつだって悲しいものだ。だが、アンリにはそれ以上の理由があったのだ。
ゆっくりと近付き、力が抜けたようにエメラリーンの前で膝をつき崩れ落ちたアンリに、彼女は目を細めて微笑みかけた。そして彼女は初めて椅子から立ち上がった。淡い世界が揺れる。ガラガラと崩壊していく世界の中、彼女は微笑み両手を広げた。そしてゆっくりと、彼を包み込もうとする。
「大丈夫。いらっしゃい、私の愛する――」
その直後、腕が体に触れる前に、エメラリーンはエメラリーンではなく見覚えのある別の女性に変わっていた。だが、
「あ、ああ……」
赤。ぬるりとした赤が咲き、胸元を大きく彩る。
自分の空いていた右手は鋭利な刃物に変わり、それは真っ赤に染まっている。美しい白が、赤く染まる。
胸が苦しい。呼吸が苦しい。
殺してしまった、大事な人を。殺してしまった、自分を愛してくれた人を。
「アンリ、おいアンリ!」
荒い自分の呼吸で目覚める。チカチカとする視界。部屋は明るくなっていて、見るとルームメイトのフレッドが心配そうに顔を覗き込んでいた。表情は強ばっている。
ふと自分の頬に手をやると、濡れていた。その手は冷たく、震えている。
何度か深呼吸をして、やっと口を開く。
「大丈夫です。起こしてごめんなさい。僕には構わないでも大丈夫ですから」
「……」
悪い夢を見ました、子供みたいですね、などと言い笑顔を作って目を逸らすと、フレッドは何か言いたそうにこちらを見ていたが、やがて口を開く。
「そっか。無理するなよ」
彼は暫くして明かりを消し、二段ベッドの上に戻っていった。
ベッドの隅で膝を抱え、アンリは一人放心していた。
暗闇の中を走る、走る。恐怖と不安に押し潰されそうになりながら、死体の山を、ただ裸足で駆ける。
ずっと自分の中にいたエメラリーンという存在は謎であるが、彼女の見た目は昔よく干渉してきた一人の研究員と酷似していた。服装は違うし、目もあんなに真っ白ではなかったが。
その研究員の名前は知らない。だがその存在はよく覚えている。ミクスくらいには。ミクス以外の人間は苦手であったが、彼女には他の大人達と違って、子供たちに対する愛を感じたからだ。だがそれも無駄なもの。みんな等しくただのモルモットとなる。そう思っていたのだが、彼女の愛は決して無駄ではなかった。彼女の愛は、彼女が死してもなおアンリに降り注がれていたのだ。エメラリーンとして、記憶としては覚えてなどいなくても、アンリに常に寄り添ってくれていた。とある昔にエメラリーンが言った通り、この優しさもまた自分自身……つまり、自己防衛なのかもしれない。エメラリーンという存在自体もまた。
仕方の無かったことと言えど、自分を愛してくれていた彼女を殺したのは自分だと知った時から、自分自身が許せなかった。時々、生きている意味さえ問うほどに。知らなかった訳では無い。極東のユリーカで記憶が戻った時に、その事実は何となく知っていた。その時は、自分を少し呪った。だが、こんなにはっきり、今さっき自分の目の前で起こった出来事のように、その事実が叩きつけられたことは無かった。手の生温い血の感触がまだ残っているようで、とても気持ちが悪い。今すぐにでも手を洗いたいが、フレッドが起きてしまう。
名前も知らない、愛しい人。彼女によく似たエメラリーンを見ると、心が安らぐ。と同時に、心が苦しい。だが今何を思おうともう会えないのだ。エメラリーンは別れを告げ、部屋を壊し、そして自ら正体を明かした。普段優しいエメラリーンが最後にアンリに対してこんな仕打ちをしたということは、やはり恨まれているのだ。
ちくちくと左目が痛む。彼女を裏切った自分に対して恨んだ結果受けた呪いだと言うのなら、仕方の無いことだと思う。実際あれからの記憶は本当に無く真偽は分からないが、どちらにせよ因果応報というやつだろう。苦しみながら、罪を償い生き続けるのが使命だというのならそうなのだろう。エメラリーンに聞いておけばよかった。彼女は背中を押してくれる。
そんなことを考えていると、妙に落ち着いてきて、窓の外の夜が明るく感じられた。そっと耳を澄ませれば、フレッドの寝息が聞こえていた。随分と長い時間が経ったのかもしれない。アンリはそっと立ち上がり、音を最小限に抑えながら、部屋を出、夜のヴァルニアを駆けていった。
街は静かだった。隣のテトロライアに比べ、夜は眠る街がヴァルニアである。
特に用事がある訳では無く、気を紛らわせようと出てきたのだが、どこからか小さな悪魔がかさこそと音を立てる。チリリとその度に目の痛みを感じた。
「ティテラニヴァーチェ」
{はぁい。あんたも元気ね}
闇夜に溶け込むような黒が、右手から
「そうかもね」
{……!?}
ティテラニヴァーチェは驚いて、目を見開いた。
{声が聞こえるの?私が見えるの!?}
「……」
アンリに彼女が見えることはない。それは変わらなかった。
彼らが悪魔と呼ぶ存在の生息域は主に森で、街に悪魔は出ない。だがそんな悪魔の気配にただならぬものを感じて、アンリは武器を展開させ警戒していたのだが、突如ふわりと殺気0の何かが飛んできた。
「……おっと」
ぽすっと手の中に収まったものを見れば、黒くて丸い生き物。大きな金の二つの目に、貧相な頭髪と足を持っていた――
「ムガイ……」
人畜無害なその悪魔は、一部でムガイと渾名を付けられている。それを離すと、その悪魔はぴょんと飛び、こちらを一度見てペタペタと路地裏の中に入っていった。立ち尽くしていると、彼(?)はこちらを振り返り、少し進んではまたこちらを振り返った。
「来いってこと……?」
アンリはそれを追いかけ路地裏に入っていった。
路地裏を照らすのは月明かりのみ。うっすらと見える先ほどの悪魔は、ペタペタと音を立て、地面を走り、やがて主の元へと辿り着くと、その足元に落ち着いた。
アンリはこんな所に人がいることに驚いた。その人物はゆっくりと歩み出で、月明かりの下へと出てきた。真っ黒なフードを被った人物。
「こんばんは」
声は意外にも若く、女性のものだった。アンリにはどこか引っかかる所があった。
「その声、どこかで。――あなたには……」
「やめて!」
「!?」
突然の拒絶に驚く。彼女は、しばらくしてから小さな声で呟いた。
「思い出さなくて、いいんですの」
そして覚悟を決めたように、こちらを真っ直ぐと見た。さっきまでは見えなかった、金の瞳が覗く。
「リィンリィンは……悪魔ですわ」
そう言いばさりとフードを脱ぎ捨てた。月明かりに目立つ、白銀に輝く頭髪。光る金の目。白い肌に尖った耳。紛れもない2型悪魔である。
「……」
リィンリィンと名乗った悪魔は、何も言わないアンリに恐る恐る訊いた。
「リィンリィンを、殺さないんですの……?」
アンリは頷いた。意外にもリィンリィンはこれには驚いた。彼女の知っていた昔のアンリなら、悪魔と分かるやいなや殺していただろう。悪魔のことは絶対的に悪で、殺すべき存在だと思っていたはずだからだ。
思案するリィンリィンをよそに、アンリの呼吸が突然乱れる。何かに誘発されたのか、痛みが強くなったのだ。リィンリィンは戸惑いつつ。近づかないようにして、満を持して口を開く。
「その痛みの理由を知りたくはありませんの?」
「なん、だって……?」
絞り出した声。リィンリィンは、一拍置いてから言葉を続けた。金の瞳が真っ直ぐ射抜く。
「リィンリィンと共に来れば、教えてあげますわ。……選ぶんですわ。リィンリィンと共に来て、真実を知るか、それとも、ここで誘いを断って、まだ苦しみ続けるか」
実際苦しんでいる最中にそこから助かる道を提示するのは些か気が引けるものの、ずるい手だとしても使わぬ義理はない。それほど手に入れたいものなのだから。けれど、相手は段々と治まってきたのか深呼吸一つすると、俯いたまま首を横に振った。リィンリィンにはそれが驚きだった。
「どうして……?」
彼は顔を上げてゆっくりと語る。
「まだ、手放せません。初めて手に入れた大事なものだから」
そう言い、こちらを一瞥すると、立ち去ってしまった。一人残されたリィンリィンは、その背の消えていった方を見たまま呟く。
「ああ、振られてしまいましたわ」
一世一代の告白(?)を一言で断られたリィンリィンであったが、彼女の心境は失恋のそれではなかった。
足元の1型悪魔がミィと鳴く。
「カイワレ、」
それを抱き上げると、リィンリィンは首を振った。
「もちろん、こんなことでは諦めませんわ」
そしてそれを抱き抱えたまま路地裏の奥、暗闇に消えていく。
「もう、見ているだけはやめたんですの。そうですわね……彼だって、今度はきっと向こうからやって来ますわ」
腹を括った乙女は実に強かった。
◆◇◆◇◆
次の日のこと。この日は外に仕事があった。アーサー組、つまりメンバーはアーサー、アンリ、アルモニカの三人に割り振られたとある任務である。
三人でエントランスに向かう途中、アーサーがアンリの顔を見て、ずっと思っていたことを口にした。
「お前、顔色悪いぞ」
「え?」
当のアンリは戸惑ったような表情を見せたものの、何か心当たりがあったような顔をして、「ああ、ちょっと寝不足で」と笑ってみせた。隣のアルモニカが心配そうに彼の顔をのぞき込んだ。
「寝不足って……大丈夫なの?」
「大丈夫です」
そうきっぱりと断言したアンリ。彼の様子をまじまじと見ていたアルモニカだったが、何を思ったのか「いくわよ」と言うと突然腹に拳を繰り出した。
「!?」
「おい何やってんだアル!」
もろに食らって倒れたアンリに、アルモニカは言い放つ。
「私の遅い拳を避けられないくらいの体調だというのなら、連れていけない。寝てなさい」
腹を押さえて起き上がったアンリ。アーサーは宥めるように言う。
「アル、いくらなんでも」
「そうです僕は行けます」
「寝てなさい!」
「あ、はい……」
彼女の怒気に押されて渋々受け入れたといった様子だ。アーサーは頭を掻いた。
「うーん仕方ねえな、俺一人で行くかあ」
「えっ?三人でこなす筈の任務なのに、一人で行って大丈夫なの?」
彼はふふんと鼻を鳴らし、得げに腕を組む。
「おう、俺を舐めるなよ。これでも副隊長、そして、ついこの前なんて一級格上げされたからな。今までの俺とは違うぜ」
「でも僕アーサーさんに勝ったことありますよ」
「うるせえ!」
「えっ、ていうか、私は……?」
「こいつを見といてくれ」
「僕寝てるだけですよ」
「こいつ絶対後からついてくるから見張っといてくれ。頼むよ」
暫く考えてから、アルモニカは頷いた。
「確かにそれはあるかもね……」
「酷いですね、何故バレた」
「ほらな」
アーサーは、手元の書類から一つ取り出し何やら書き込むと、アルモニカに手渡し事務に持っていくよう頼んだ。出撃人数の変更だろう。
「じゃあ行ってくるわ」
行ってらっしゃいと、二人は見送った。
◆◇◆◇◆
三番隊の面々が自由に使う部屋。形式的にはミーティングルームと呼ばれているその部屋の片隅の簡易ベッドでアンリは横になっていた。傍らにはアルモニカが椅子に座って本を広げている。
「アルさんごめんなさい」
「なんで謝るの?殴ったのは私なのに」
「いえ、そのことではなくて。本来なら任務に出てたはずなのに、僕のせいでこんなことに付き合わされて」
それを聞いたアルモニカは、ふふっと笑った。
「それを言うなら、謝るべきはアーサーに、でしょ?それに私、サボれて万々歳だわ」
「あはは、そうでしたか」
「――にしても、監視と言えど私がこんなところにいたら眠れない?席外そうか?」
「あーいえ、どちらにせよ眠れる気はしないので」
そう言い、天井を見つめた。そう言えば、と彼はぼんやり零す。
「師匠に護身の十字架をあげてから、災難によく遭っている気がします」
「師匠?」
「ああ、東にいた時に、剣とかその他諸々の師匠です。結構あの人の影響受けているのかも」
「へえ、でもそうだね。ならきっとその人はすごい人ね」
「アーサーさんにはまともなやつじゃないだろうと言われました」
「同じ意味よ」
「はは、どういう意味ですか」
楽しそうに徒然なる会話をしていたが、ふとアルモニカが真面目な様子で切り出す。
「アンリ、あなた悩み事でもあるんでしょう」
「……どうしてそう思うんですか?」
「眠れないほどなんて、そんなものでしょ?それに、こっちに帰ってきてからアンリなんか変なんだもん」
「……」
すっかり閉口してしまったアンリに、アルモニカは少し考えた後口を開く。
「私にも最近悩み事があるの。良かったら聞いてくれる?」
彼女は語りはじめた。
数日前、書類の点検をしていて気付いたことを聞きに、レイクレビン上級官の部屋を覗きに行ったアルモニカ。だが彼はおらず、変わりに見たことない人物がいた。
「おや、レイクレビンに用があったのかな?残念ながら彼は今いないよ。代わりに聞いておこうか?」
その人物は中年男性。白と黒の制服を身につけていた。黒い長髪、前髪は長く目が隠れている。赤い腕章を付けているが、どこ所属なのか全く分からない。けれど見覚えのある、確か前隊長であるクロウ・ベルガモットが胸に付けていたのと同じ徽章を付けていた。金で、西を示す十字、確か、テトラールキの証。
アルモニカがまじまじと見ていると、彼は「うん?」と聞き返した。
「あ、いえ。すみません、また伺います」
「そうかい。ついでに仕事を頼みたいんだが」
「仕事?」
その人物は彼女にファイルを手渡した。
「これを図書室から拝借したんだが、返すのが億劫でな」
「はあ……」
アルモニカがそれを受け取りよく見ると、持ち出し禁止になっていた。
「そうなんだよ。俺が返しに行くと怒られてしまうからな。なに心配はいらない。団長から、とそう伝えてくれ」
そう言い彼は微笑むと、部屋を出ていってしまった。
図書室に行くまでに、そのファイルをよく見ると、気になる言葉を見つけた。
建物の地下にある図書室、そこへそのファイルを返してから、アルモニカは探し物を始めた。彼女にとって一番重要な問題に関する情報。彼女の母親が死んだ事件について。
図書室には様々な事件や任務のレポートがファイリングされ並べられている。しかし、幸い日付ははっきりしているので探すのは容易だった。
アルモニカにとって唯一の家族は最愛の母親だった。仕事に出て仕事場に泊まることも多く、あまり家にはいなかったが、時々帰ってきてくれる。血の繋がっていない、だが、本当にこの人の子供だったらいいのになと思えるそんな人だった。だがある時から、彼女は帰って来なくなった。疑念と言いしれぬ不安の中、風の噂で聞いた。母親は悪魔に殺されたと。……忘れもしないその日。
しかし、様々な資料を見ていくにつれ、母親が悪魔に殺されたという確証は無くなっていった。代わりに、彼女が働いていた職場で何かあったということが分かった。名は、カナソーニャ・ロヴァイ研究所。だがそれより、その時は、悪魔が悪くなかったということにアルモニカは衝撃を受けていた。彼女の幸せを奪った悪魔。悪魔が憎くて憎くてその憎しみでこの世に立っていたようなアルモニカは、教団員となり任務で悪魔と退治する度、鬼のように駆け回っていた。それが間違ったものだと分かった時、今まで何をしてきたのだろう。これからどうすればいいのだろうという感覚に陥ったのだ。
「でもね」
アルモニカはゆっくりと続けた。
「憎しみで生きてるなんて、生きてるなんて言えない。私、きっとちゃんと生きてなかったのよ」
休日にアンリと共に出掛けた帰り、アルモニカが言った『私、ちゃんと生きる』という言葉を思い出した。そしてその意味も。彼女は自らの運命をしっかりと受け止め、そして受容している。話すアルモニカの横顔は、とても眩しく見えた。
「今回の任務の、悪魔の巣食う研究所というのは、私のお母さんの働いてた場所。これが終われば取り壊される。もう、ここできっぱり終わりにしなくちゃ」
そう言い笑顔を作った。
「強いんですねアルさんは」
「そう?」
「はい」
僕なんかと違って。そんなこと、口には出さない。
「聞いてくれてありがとう」
アンリは首を横に振る。
アルモニカは、「それでね、」と続けた。
「今すぐじゃなくていい。いつかでいいから、話して欲しい。どうか私を頼って欲しいの。だって、寂しいじゃない」
アルモニカにとってアンリの事は友達のような、仲間のような、弟のような存在だった。だがしばらく見ない間に少し変わった彼が、何かを抱えているのは知っている。けれど、それが何なのかは分からない。話してくれない。話したくないのかもしれない。無理に聞くのは良くないかもしれない。けれど、私がアンリの力になりたい気持ちは変わらない。――そんなことを思いながらの言葉だったが、アンリは「いつか」と笑った。きっと、いつになっても言ってくれないのだ。アルモニカはもう理解していた。
「僕、最近眠れなくて。でも、アルさんと話してると眠くなってきました。なんだか心地いいですね」
そう言って柔らかく微笑んだ彼の笑顔を見て、心が少しきゅっと締め付けられる感覚に陥ったのは、恐らく気の所為ではない。
暫くして、そのまますっかり眠りこけた彼の額に手を当て、無意識にアルモニカはアンリを見つめていたが、はっとしたように手を離すと、頭を振った。
――人の心を読むなんて、人の意識に入り込むなんて、絶対にできない。もう、したくない。
心を落ち着かせるように、アルモニカはそっと部屋を出ていった。本は、置きっぱなしのまま。
◆◇◆◇◆
【テトロライア黒の森 某所】
深い森の奥にひっそりと立つ無機質な建物。そのとある一室。薄暗い中、男はテーブルに手稿や地図、チェス盤やカードなど、ありとあらゆるものを広げ頭を抱えていた。
「おや中々お困りのようで」
突然声のした方を男が振り向くと、出入口から真っ白な男が入ってきていた。真っ白な帽子、真っ白なコートにスーツ。全く酔狂なこの男の名はジュディ、又はシロウと言った。
「おお、シロですか……帰ってきてくれて嬉しいですよ。そう、あなたに頼みたいことが……」
そう言い立ち上がった男はエネミ・リラウィッチという名の錬金術師だった。いつも余裕のある仕草や表情をしていたが、そんな彼には似つかわしくない目の下の隈、髪は少し乱れ、いつもパリッとしていた筈のシャツには皺が入ったままだ。
「ああそんなことより父上よ。俺は言いたいことがあって来たんだ」
ジュディは一歩踏み出して、大事な筈の父上の言葉を遮った。エネミは何か察したようで、彼の顔を見つめた。
「シロ、何の真似です」
「父上よ、俺はあなたを見限った」
ジュディは強い口調でそう言い放った。エネミはしばらく放心したようにシロを見ていたが、やがてぷいとそっぽを向き、忙しそうにテーブルの上の手稿に目をやる。
「まあいいでしょう。あなたがいなくなったところで、花の開花時期くらいもう私にも分かりますからね」
「そう」
ジュディは目を細めた。
「理由はね、」
「……?」
不審な表情を浮かべたエネミをよそに、ジュディは右に避けると、彼の後から黒髪の男が現れた。
「……クロ」
エネミの表情が固まった。
「父上よ、俺は今まで父上を信用してきました。でももう信用しない。クロと俺をバラバラにしたのは、俺に見つけられないようにしたのは、父上……いや、お前だと分かったからだ」
「シロ、」
「お前の口からその名を呼ばないでくれるかな。さあ行こうクロ」
踵を返して立ち去っていくシロと、彼とエネミを一度見てからシロの後を追うベルガモット。
「待ちなさい、シロ、クロ、待ちなさい……!」
必死に呼び止めるも、彼らは振り向く事は無かった。
建物から出て、ジュディは黒い液体の入った瓶を地面に叩きつける。それに呑まれた二人は、瞬時に離れた場所に移動した。
「あの老いぼれ、あの人はもうだめだなあ」
彼を横目で見たベルガモットは、一言も喋らない。
「まあ、殴りかからなかっただけ褒めて欲しいものだね」
そう言い笑った彼に対し、ベルガモットの表情筋は動かない。だが、彼は立ち止まってジュディの顔を見た。振り返るジュディはベルガモットの顔を見ただけで、大体の言いたいことが分かるようだ。
「あの人をあまり舐めない方がいい?ああ、クロの方が先にあの人のこと知ってるからね。でも長くいたのは俺の方だけど?」
「……」
「あの人を半分ずつにしたのが俺らみたいなもんだから、二人揃うと厄介だと思ってるんだ。一番怖い相手は自分だなんて、あの人らしいよ。あの手この手で俺達を引き裂こうとするだろうけど、もう二度とそうはさせないよ」
そうしてベルガモットの手を強引に取ると、また歩き出す。
「これからどうするの、だって?」
悪魔の集団から身を引き、父上とも縁を切ったジュディの行く末を案じているのだ。だが、彼はそんな無計画に進む者ではなかった。
「行く宛は決まっているよ」
「俺達は鷹になるのさ」
意味深な彼のセリフだが、ベルガモットには何のことか分からなかった。何故ならその人物のことを知らなかったからだ。けれど、その人物とはベルガモットが別の場所で知っていた人物であることを彼らはまだ知らない。
33話へ









